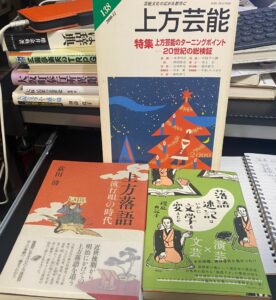
ここにきて思い知ったことがあります。
インターネットもAIも思ったより役に立ってくれない、という事。
いや、当たり前のことと言えばそうなのですが、使いこなすことができていない悔しさも含めて少し悪態をついてしまいました。いや、すべては自分の不徳の致すところなのですが。
現在、私は「明治時代の上方落語とはどんなものだったのか」という疑問を解消すべく調べもの三昧の日々をすごしております。上方落語の解説動画っぽい物を作成するにあたって「小拍子、見台、膝隠しは昔の名残」という通説に対して「ほたら、元の形はどんな使われ方をしとったの?」という素朴な疑問が出てしまいまして。
これは動画内でも語ることになるとは思うのですが、上方落語黄金期と言われた明治の頃の上方落語は非常に賑やかで派手な物が多かったような資料が残っております。いわゆる「はめもの」と言われる下座音楽を用いた演出(現在でいうところの『狐芝居』『皿屋敷』『七段目』など)が多用された落語は、戦災によって道具一式が焼けてしまった時に東京風の素ばなしに容易に変換できるものではなかったというような記述が落語研究家の宇井夢愁先生の著作に見られます。
仮説としては明治時代、二代目桂文枝の桂派が素ばなしを前面に押し出したことに対して、月亭文都の浪花三友派が取り入れた派手で賑やかな興行が元になったのではないかという物です。一通りの遊びを終えた旦那衆が平野町・松屋町の此花館、新地の永楽館に顔を出す寄席というのはさぞかし歌に踊りに質の高い演芸を提供されていたのではないかと、その裏付けとして当時の寄席の出し物がどんなものかと。
そして冒頭に戻るのですが「膨大な電子の海の中からそれらの記述を発見することはできなかった」のでありますよ。なんなら、間違った情報が堂々と書き込まれ、それがコピペされて広まっているのを見つけてしまったり。
なので資料は複数当たらなくてはいけませんよね。
ついに落語速記と明治の流行り歌まで足を突っ込んでおります。ここに歌舞伎と浄瑠璃、講談まで入ってきますともう収拾がつかなくなってしまいそうですが、まーなるようになりますか。
それでも分かりやすく咀嚼して、少しでも興味を持ってもらえるようにアウトプットできれば良いなと思う次第。
さてどうなりますやら。
やしおり拝
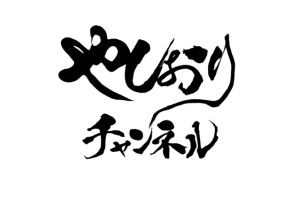



コメント